目次
ChatGPTが変える、業務時間の使い方
毎日の業務に追われ、本来注力すべき仕事に時間を割けない。
多くのビジネスパーソンが直面するこの課題は、生成AIの登場によって解決の糸口を見出しつつある。ChatGPTをはじめとする生成AIツールは、単なる作業効率化にとどまらず、業務そのものの質を変える可能性を持っている。
実際、MIXIが2025年3月から全従業員に導入したChatGPT Enterpriseでは、わずか3ヶ月で月間約17,600時間の業務時間削減を実現した。これは利用者1人あたり月間約11時間に相当し、利用者の99%が生産性向上を実感している。一部のプロジェクトでは業務時間を90%以上削減するという顕著な成果も現れている。
重要なのは、この削減された時間をどう活用するかである。単なるコスト削減ではなく、思考を深める時間、創造的な仕事に向き合う時間へと転換していくこと。それが、生成AIを導入する本質的な意義といえるだろう。

ChatGPTで効率化できる業務領域
生成AIの活用範囲は想像以上に広い。
NSSスマートコンサルティングが実施した調査によれば、ChatGPTを業務で活用している会社員の約半数が「文章の作成・要約・校正」に使用しており、次いで「情報検索」が48.4%、「情報処理・データ分析」が42.2%という結果が出ている。約8割の利用者が週に数日から毎日という頻度で日常的に使っているという事実は、生成AIがすでに業務インフラの一部となりつつあることを示している。
文章作成と編集業務の効率化
メールやチャットの作成は、定型的でありながら一定の時間を要する業務である。ChatGPTを活用すれば、取引先へのお礼メール、営業メール、問い合わせへの返信文などを数秒で生成できる。プロンプトに細かく条件を記載することで、用途に応じた敬語やビジネスマナーが反映され、誤字脱字を防ぎつつ一定の品質を保てる。
企画書や会議の議事録、提案書、プレゼン資料の草案といった文書作成も同様である。ChatGPTを活用すれば、用途に適した基本的な枠組みが瞬時に生成されることから、担当者が一から文書を作成する必要がなく、修正や調整のみで済む。箇条書きや表形式を盛り込むことも可能だ。
情報収集と分析業務の再設計
長文文書の要約にもChatGPTは力を発揮する。会議資料や競合他社のレポート、Webサイトの記事など、従来は読み込みに時間がかかっていた資料を、指定の文字数や要点に絞って瞬時に要約できる。これにより、情報収集の効率が劇的に向上する。
MIXIの事例では、コンプライアンス本部法務部が利用規約確認カスタムGPTを導入したことで、通常30分から1時間を要していた確認作業が約10分で対応可能になり、月間で約40時間の業務効率化を実現した。業務負荷の軽減に加えて委託費削減にも貢献している。
専門業務における活用可能性
職種や部署によって、ChatGPTの活用方法は多様である。
マーケティング部門では企画業務の効率化が進んでいる。MIXIのみてねマーケティング部では、「GCT: Creative Planning」の活用により月間約28時間の工数削減を実現し、レビューの軽減や提案力の向上など、チーム全体の生産性と創造性に寄与している。
経営推進部門では予算に関わる申請や問合せ業務の利便性向上を目的としたアシスタントBotの構築が行われている。Bot支援でプロジェクト管理ツールの申請業務を簡略化し、1件あたりの所要時間を約50%削減、年間で約150時間の業務効率化を見込んでいる。
投資事業部では「VCファンド初期検討サポートくん」による仮説検証が行われ、スタートアップやVCファンド投資の初期検討における情報整理とレポート作成を自動化。1社あたりの作業時間を最大90%短縮し、年間約108時間の業務削減効果に相当する成果を上げている。

業務時間削減を実現する具体的手順
ChatGPTを導入しただけでは、業務効率化は実現しない。
重要なのは、どのように業務フローに組み込み、組織全体で使いこなす状態を作るかである。MIXIの事例から学べるのは、教育プログラムと現場起点の活用推進が成功の鍵だということだ。
段階的な導入と教育体制の構築
MIXIでは、ChatGPT Enterpriseの全社導入後、OpenAIとともに全従業員を対象とした「ChatGPT 101トレーニング」を実施した。新卒社員向けワークショップやエンジニア向けハッカソンなど、対象者に応じた社内教育プログラムを提供し、高度なAI人材の育成に努めている。
こうした取り組みにより、全社導入から3ヶ月未満でアクティブユーザー率が80%に到達し、1,800個以上のカスタムGPTが自発的に作成されるようになった。生成AIを使いこなす企業文化が着実に根付いている。
プロンプト設計の基本原則
ChatGPTから適切な回答を得るには、プロンプトの設計が重要である。
基本となるのは、目的を明確にすること。「取引先へのお礼メールを作成してください」という指示だけでなく、「先日の契約締結へのお礼」「今後のスケジュール」といった具体的な内容を盛り込むことで、より見込み通りの結果が得られる。
文書作成の場合、構成に必要な項目を事前に整理しておくと効果的である。「タイトル、現状の課題、提案内容・課題の解決策、提案内容の根拠、提案内容から得られるメリット、補足情報」といった構成を指定することで、体系的な文書が生成される。
要約を依頼する際は、指定の文字数や要点の数を明示する。「以下の文章を300文字で要約してください」「3つの要点にまとめてください」といった具体的な指示が、期待する成果物を得るための鍵となる。
業務フローへの組み込み方
ChatGPTを単発で使うのではなく、日常業務のフローに組み込むことが重要である。
例えば、会議後の議事録作成を自動化する。会議の音声を文字起こしし、その内容をChatGPTに要約させることで、議事録作成の時間を大幅に削減できる。メール対応では、問い合わせ内容をChatGPTに入力し、返信文の草案を生成させることで、担当者は微調整のみで済む。
資料作成では、まず構成案をChatGPTに提案させ、その骨組みに沿って詳細を肉付けしていく。このように、作業の各段階でChatGPTを活用することで、業務全体の効率が向上する。

効率化を成功させるための重要ポイント
業務効率化は、ツールを導入すれば自動的に実現するものではない。
組織として、個人として、どのような姿勢で取り組むかが成果を左右する。
試行と思考のサイクルを回す
ChatGPTの活用で時間が削減されたら、その時間を何に使うかを明確にすることが重要である。単なる作業時間の短縮で終わらせるのではなく、試行回数を増やし、思考を深める時間に転換する。
例えば、企画書作成の時間が半分になったなら、その分だけ複数の案を検討し、比較検討する時間に充てる。メール対応が効率化されたなら、顧客との関係構築により多くの時間を割く。このように、削減された時間を質の向上につなげることが、真の業務効率化といえる。
情報の正確性を担保する仕組み
ChatGPTは膨大な情報を学習しているが、常に正確な情報を提供するとは限らない。
特に最新の情報や専門的な内容については、必ず人間が確認する必要がある。MIXIの事例でも、カスタムGPTを活用しながら、最終的な判断は人間が行う体制を整えている。
重要なのは、ChatGPTを「思考のパートナー」として位置づけることである。完全に任せるのではなく、アイデアの壁打ち相手として活用し、最終的な判断は人間が行う。この姿勢が、質の高い成果物を生み出す鍵となる。
セキュリティとコンプライアンスの徹底
業務でChatGPTを活用する際、機密情報の取り扱いには細心の注意が必要である。
無料版のChatGPTでは、入力した情報が学習データとして使用される可能性がある。企業で利用する場合は、ChatGPT EnterpriseやMicrosoft Copilotなど、企業向けのサービスを選択することが望ましい。これらのサービスでは、入力データが学習に使用されない設定が可能であり、セキュリティ面でも強化されている。
また、社内ガイドラインを整備し、機密情報ラベルに応じた適切な情報入力を徹底することも重要である。MIXIでは、社内ガイドラインに基づき、各種生成AIツールの業務活用を本格化させている。

ChatGPTと他の生成AIツールの使い分け
生成AIツールは、ChatGPTだけではない。
Microsoft CopilotやGoogle Geminiなど、それぞれに特徴があり、用途によって使い分けることで、さらなる効率化が可能になる。
Microsoft Copilotの特性と活用場面
Microsoft CopilotはGPT-4をベースとしながら、Microsoft Graphと連携することで、社内データを活用した業務支援が可能である。WordやExcel、PowerPointといったMicrosoft 365アプリケーションと統合されており、文書作成やデータ分析、プレゼンテーション作成などで威力を発揮する。
特に、会議中の発言をリアルタイムで要約する機能や、メール履歴から必要な情報を迅速に検索する機能は、日常業務の効率化に直結する。Microsoft製品を中心に業務を行っている企業にとって、Copilotは自然な選択肢となるだろう。
Google Geminiの強みと適用領域
Google Geminiは、Googleの検索技術と統合されており、最新情報へのアクセスに優れている。
また、Google Workspaceとのシームレスな連携により、GmailやGoogle ドキュメント、Google スプレッドシートでの作業効率化が期待できる。特に、リアルタイムでの情報検索や、複数の情報源を横断した分析が必要な場面で力を発揮する。
ツール選択の判断基準
どのツールを選ぶかは、既存の業務環境と目的によって決まる。
Microsoft 365を中心に業務を行っているならCopilot、Google Workspaceを使用しているならGemini、より汎用的な用途や最新のAI機能を試したいならChatGPTといった具合である。重要なのは、複数のツールを併用し、それぞれの強みを活かすことである。
株式会社グレイトフルエージェントの生成AI研修サービスでは、ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Geminiの3つのツールに対応しており、企業の業務環境に応じた最適な活用方法を学ぶことができる。

組織全体でAI活用を推進する体制づくり
個人レベルでの活用にとどまらず、組織全体でAI活用を推進することが、競争力の源泉となる。
MIXIでは、2024年12月に取締役を主管とする「AI推進委員会」を発足させ、各部門にAIアンバサダーを配置することで、現場起点でのAI活用を推進している。AI関連プロジェクトは2025年7月末時点で300件を超えて進行中であり、個人レベルでの業務効率化にとどまらず、コスト最適化・付加価値創出・新規事業構想などを目的とした取り組みが広がっている。
AIアンバサダー制度の効果
各部門にAIアンバサダーを配置することで、現場の課題に即したAI活用が促進される。
アンバサダーは、部門内でのAI活用事例を収集し、横展開する役割を担う。また、新しい活用方法を試し、その結果を共有することで、組織全体の知見が蓄積されていく。この仕組みにより、トップダウンではなくボトムアップでのAI活用が進み、現場に根付いた実践的な活用が実現する。
継続的な学習環境の整備
AI技術は日々進化しており、継続的な学習が欠かせない。
定期的な研修やワークショップを開催し、最新の活用事例や技術動向を共有することが重要である。また、社内で成功事例を積極的に発信し、他部門への横展開を促すことで、組織全体のAIリテラシーが向上していく。
株式会社グレイトフルエージェントの生成AI研修サービスでは、全5回構成(各2.5時間、合計12.5時間)のオンライン研修を通じて、基礎から応用まで体系的に学ぶことができる。プロンプト設計とAIの基本理解から始まり、自社業務への活用領域の発見、文書作成・報告書・議事録・メール対応といった共通業務効率化、営業・人事・総務など職種別活用、現場課題をテーマにした実践ワークまで、実務に即したカリキュラムが用意されている。
業務時間削減の先にあるもの
ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務時間を削減する強力なツールである。
しかし、その本質は時間削減そのものではなく、削減された時間をどう使うかにある。思考を深める時間、創造的な仕事に向き合う時間、人との対話を大切にする時間。こうした時間を確保することが、個人の成長と組織の競争力につながる。
MIXIの事例が示すように、利用者の99%が生産性向上を実感し、89%が仕事の満足度向上を感じている。これは、単に作業が速くなったということではなく、本来やりたかった仕事に集中できるようになったことを意味している。
生成AIは特別なものではなく、道具箱のひとつである。ただし、その使い方を知っている人と知らない人では、仕事の速さも質も変わる。重要なのは、早期に導入し、使いこなす状態を作り、それを組織の文化として定着させることである。
業務効率化は、人の力を引き出すための考え方である。AIと人間の共創によって、これまで以上に価値ある仕事ができる環境を整えること。それが、これからの時代に求められる組織の姿といえるだろう。
株式会社グレイトフルエージェントの生成AI研修サービスは、実務でのAI活用スキルを体系的に習得できる法人向け教育サービスです。業務時間の約30〜35%削減を実現し、受講者の71%が「業務の質が向上した」と回答しています。人材開発支援助成金の対象で75%還元が可能なため、コストを抑えながら組織全体のAIリテラシーを向上させることができます。
実務で使える生成AIスキルを身につけるなら、今がチャンス!






















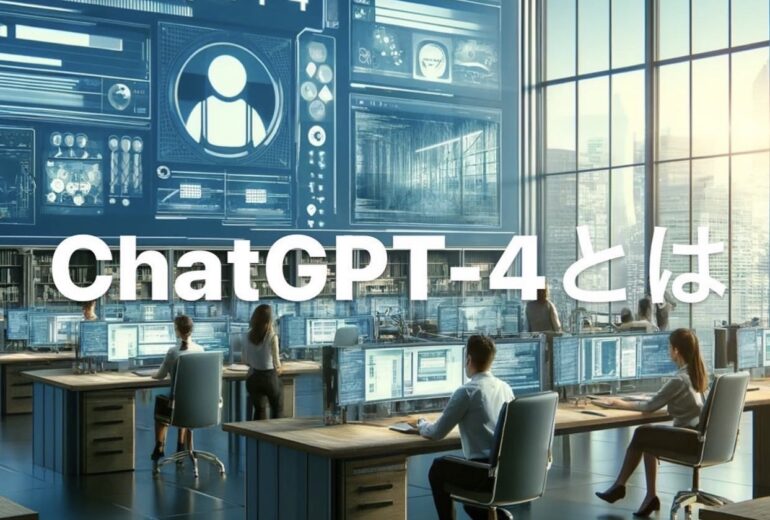


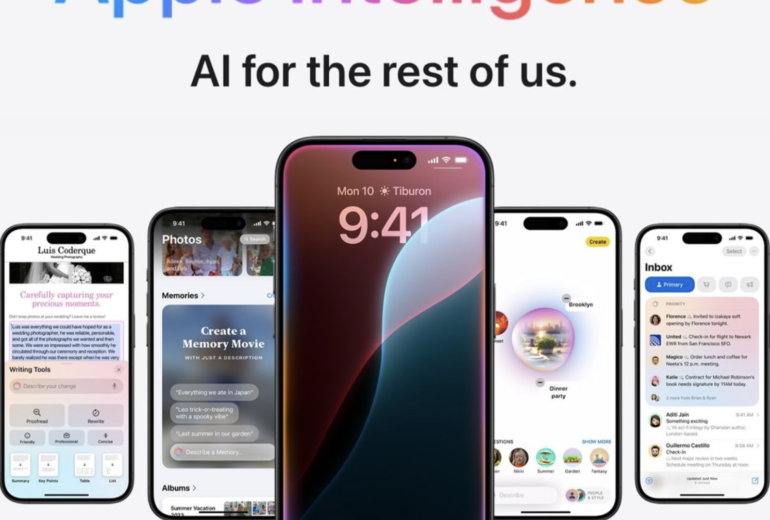


コメント