目次
AI研修と助成金の可能性
生成AIの導入が企業の競争力を左右する時代が到来した。
ChatGPTやCopilotといったツールは、もはや一部の先進企業だけのものではない。中小企業においても、業務効率化や生産性向上の手段として、AI活用が現実的な選択肢となっている。ただし、そこには一つの壁がある。研修コストである。社員にAIスキルを習得させるには、相応の投資が必要となる。その壁を取り払う仕組みが、厚生労働省の「人材開発支援助成金」である。
この制度を活用すれば、研修費用の最大75%が助成される。つまり、実質的な負担を大幅に抑えながら、社員の能力開発を進めることができる。本記事では、AI研修に助成金を活用する具体的な方法と、申請から受給までの実務的な手順を整理する。
人材開発支援助成金とは何か
人材開発支援助成金は、企業が従業員に対して職務関連の専門知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度である。雇用保険財源で運用されており、審査枠の競争はなく、条件を満たせば原則として支給される。
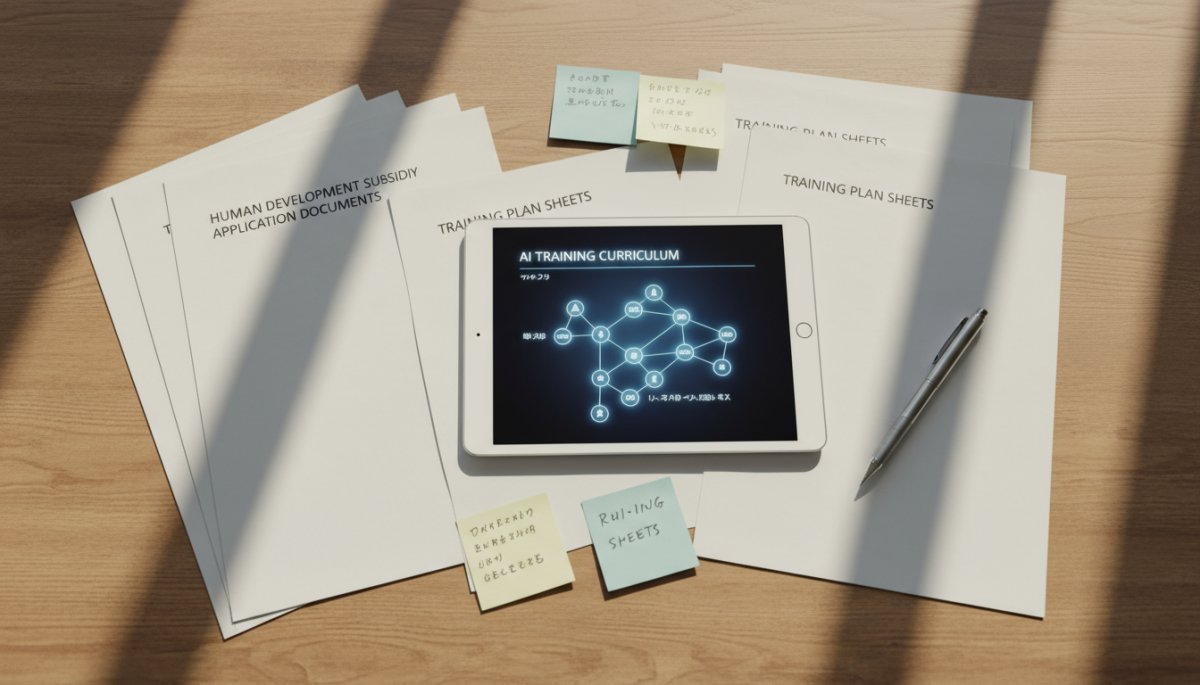
この助成金の特徴は、オンライン研修やeラーニングも対象となる点である。つまり、場所を問わず、柔軟な形式で研修を実施できる。また、正社員だけでなく、有期契約労働者やパートタイム労働者も対象に含まれる。企業規模や雇用形態を問わず、幅広い従業員の育成に活用できる仕組みといえる。
助成金の基本構造
助成金は「経費助成」と「賃金助成」の二つで構成される。経費助成は、研修そのものにかかる費用の一部を補填するものである。賃金助成は、研修を受講している時間に支払う賃金の一部を補填する。この二つを組み合わせることで、企業の実質的な負担を軽減する。
助成率や助成額は、企業規模やコースによって異なる。中小企業の場合、経費助成率は最大75%、賃金助成は1人1時間あたり最大1,000円となる。大企業の場合は、経費助成率が最大60%、賃金助成が1人1時間あたり最大500円である。
AI研修が対象となる理由
生成AIに関する研修は、「高度デジタル人材」の育成として位置づけられている。これは、2025年度の制度改定において明確化された。DX推進やデジタル技術を活用した業務改革に必要なスキルとして、生成AIの活用能力が認められたのである。
したがって、ChatGPTやCopilot、Geminiといったツールの操作方法や、プロンプト設計の技術を習得するための研修は、助成金の対象となる。ただし、単なる操作講習ではなく、職務に関連した知識・技能の習得を目的とする必要がある。
AI研修で活用できる3つのコース
人材開発支援助成金には複数のコースが存在する。AI研修で主に活用されるのは、以下の3つである。それぞれの特徴と、どのような場合に適しているかを整理する。

人材育成支援コース
このコースは、最も汎用性が高い。新人研修からDX研修まで、幅広いテーマを対象とする。AI研修においても、全社員向けの基礎講座や、部門別の応用研修など、柔軟に活用できる。ただし、助成率は他のコースと比較すると控えめである。
中小企業の場合、経費助成率は45%、賃金助成は1人1時間あたり800円となる。一定の賃金要件を満たした場合、経費助成率が60%、賃金助成が1,000円に引き上げられる。訓練時間は10時間以上が必要である。
事業展開等リスキリング支援コース
このコースは、DX推進や新規事業展開に伴う人材育成を対象とする。企業がAIを活用して業務改革を進める場合、このコースが適している。助成率が高く、中小企業の場合、経費助成率は75%、賃金助成は1人1時間あたり1,000円である。
ただし、申請には事業計画書の提出が求められる。DXやAI導入の目的、期待される効果、研修内容との関連性を明確に示す必要がある。申請のハードルはやや高いが、その分、助成額も大きい。
人への投資促進コース(高度デジタル人材訓練)
このコースは、高度IT人材の育成を目的とする。経済産業省が認定する「Reスキル講座」を受講する場合などが対象となる。生成AIに関する専門的な研修も、このコースに該当する可能性がある。
中小企業の場合、経費助成率は75%、賃金助成は1人1時間あたり1,000円である。上級者向けのプロンプト設計や、AI運用者向けの実践研修など、より専門性の高い内容に適している。
助成金の支給要件を理解する
助成金を受給するには、いくつかの要件を満たす必要がある。これらは制度設計上、明確に定められている。ただし、運用面では慎重さが求められる。書類の不備や遅延が、最大の不支給リスクとなるからである。
基本的な要件
まず、雇用保険の適用事業所であり、労働保険に加入していることが前提となる。研修を受講する従業員は、雇用保険の被保険者でなければならない。派遣労働者や役員は対象外である。
研修は、職場外訓練(OFF-JT)として実施する必要がある。つまり、通常の業務とは別に、専用の時間を設けて行う訓練である。訓練時間は10時間以上が求められる。また、訓練開始の1〜6か月前に「職業訓練実施計画届」を提出しなければならない。
研修内容に関する要件
研修内容は、職務に関連した専門的な知識や技能の習得を目的とする必要がある。単なる教養講座や、業務と無関係な内容は対象外である。AI研修の場合、業務効率化や生産性向上といった、明確な目的を設定することが重要である。

また、研修は計画に沿って実施される必要がある。計画届に記載した内容と、実際の研修内容が大きく異なる場合、助成金が支給されない可能性がある。研修カリキュラムや講師、実施時間などを、事前に明確にしておくことが求められる。
申請手続きに関する要件
研修終了後、2か月以内に支給申請を行う必要がある。申請には、賃金台帳や出席簿、研修実施報告書などの書類を添付する。これらの書類に不備があると、審査が遅れたり、支給が認められなかったりする。
特に注意すべきは、賃金台帳の記載である。研修時間中の賃金を、通常業務とは別枠で記載することが推奨される。これにより、助成額の計算が容易になり、不備を防ぐことができる。
申請から受給までの実務的な流れ
助成金の申請は、いくつかの段階を経て進められる。標準的なスケジュールは、約10週間である。ただし、準備の状況や労働局の審査状況によって、期間は前後する。以下、各段階の具体的な内容を説明する。
制度選定と計画策定(0〜4週)
まず、どのコースを活用するかを決定する。研修の目的や内容、対象者、企業の状況などを踏まえて選択する。次に、研修計画を策定する。受講人数、訓練時間、カリキュラム、講師、実施方法などを具体的に定める。
計画届の作成には、一定の時間を要する。特に、事業展開等リスキリング支援コースを選択する場合、事業計画書の作成が必要となる。DXやAI導入の目的、期待される効果、研修との関連性を、論理的に説明しなければならない。
計画届の提出(1〜4週)
計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、管轄の労働局に提出する。電子申請も可能である。2025年度の制度改定により、申請書類の重複部分が整理され、記載事項も削減された。また、自動計算機能が実装されるなど、申請の負担が軽減されている。
計画届には、研修カリキュラムや講師の経歴、受講者名簿などを添付する。これらの書類は、研修内容の妥当性や、受講者の適格性を確認するためのものである。不備があると、計画が受理されない可能性がある。
研修の実施(5〜8週)
計画届が受理されたら、計画に沿って研修を実施する。研修中は、出席簿や実施記録を作成する。これらは、後の支給申請で必要となる。また、研修内容が計画と一致していることを確認しながら進める。

AI研修の場合、基礎講座と実務演習を組み合わせることが効果的である。たとえば、Zoomやeラーニングで基礎講義を行い、その後、実務に即したプロンプト設計演習を追加する。このようなハイブリッド構成により、ROIの見える化ができ、社内での説得もしやすくなる。
支給申請(9〜10週)
研修終了後、2か月以内に支給申請を行う。申請には、賃金台帳、出席簿、研修実施報告書、領収書などを添付する。これらの書類は、研修が計画通りに実施されたこと、経費が適正に支出されたことを証明するものである。
申請書類は、電子申請ポータルにアップロードする。書類に不備があると、審査が遅れる。特に、賃金台帳や出席簿の記載には注意が必要である。研修時間と賃金の対応関係が明確でないと、助成額の計算ができない。
助成金の受給
審査が完了すると、助成金が支給される。支給までの期間は、申請状況や労働局の審査状況によって異なる。一般的には、申請から数週間から数か月程度である。支給額は、申請内容に基づいて計算される。
申請を成功させるための実務的なコツ
助成金の申請は、制度設計上は明快である。しかし、実際の運用では、いくつかの注意点がある。これらを押さえることで、申請の成功率を高めることができる。
生成AIを高度デジタル分野として明記する
計画届には、研修の目的を具体的に記載する必要がある。AI研修の場合、「業務自動化スキルの習得」「生成AIを活用した業務効率化」といった表現を用いる。これにより、研修が高度デジタル人材の育成に該当することを明確にする。
2025年度の制度改定により、生成AIが「高度デジタル人材」の対象に追加された。この点を計画届に明記することで、審査がスムーズに進む。また、研修内容が職務に関連していることを、具体的に説明することも重要である。
オンラインと実務演習のハイブリッド構成
AI研修は、オンライン形式で実施することが多い。ただし、単なる講義だけでは、実務への応用が難しい。そこで、基礎講義と実務演習を組み合わせることが効果的である。
たとえば、Zoomやeラーニングで基礎講義を行い、その後、実務に即したプロンプト設計演習を追加する。このような構成により、受講者のスキル習得が促進される。また、ROIの見える化ができるため、社内での説得もしやすくなる。
賃金台帳に研修時給を明記する
賃金台帳には、研修時間中の賃金を明記する必要がある。通常業務とは別枠で記載することで、助成額の計算が容易になる。また、不備を防ぐことができる。

賃金台帳の記載方法については、労働局に事前に確認することが推奨される。地域によって、記載方法に若干の違いがある場合がある。事前に確認しておくことで、申請後の修正を避けることができる。
よくある疑問と注意点
助成金の申請にあたって、よく寄せられる疑問がある。これらを事前に理解しておくことで、申請の準備がスムーズに進む。
研修時間が10時間未満の場合
OFF-JTが10時間未満では、助成対象外となる。ただし、複数回の短時間研修を合算することは可能である。また、OJT(職場内訓練)を併用することで、訓練時間を確保する方法もある。
AI研修の場合、基礎講座(4時間)、部門別ユースケース演習(6時間)、OJT(10時間)といった構成が考えられる。このように、OFF-JTとOJTを組み合わせることで、訓練時間の要件を満たすことができる。
地方自治体の助成金との併用
人材開発支援助成金は、地方自治体の助成金と併用することが可能である。たとえば、東京都のDX人材育成支援事業などがある。ただし、同一経費の二重請求は認められない。
併用する場合は、経費の内訳を明確にする必要がある。どの経費を国の助成金で賄い、どの経費を自治体の助成金で賄うかを、事前に整理しておく。これにより、二重請求のリスクを避けることができる。
未経験のパート社員も対象か
雇用保険に加入していれば、パート社員も対象となる。有期契約者向けのメニューを選ぶと、助成率が最大75%まで上がる。これは、非正規雇用労働者の能力開発を促進するための措置である。
AI研修の場合、未経験者向けの基礎講座を設けることが効果的である。これにより、幅広い従業員がAIスキルを習得できる。また、助成率が高いため、企業の負担も軽減される。
助成金活用の実際的な効果
助成金を活用することで、企業はどのような効果を得られるのか。ここでは、具体的な数値をもとに、その効果を整理する。
コスト削減の効果
中小企業が事業展開等リスキリング支援コースを活用した場合、経費助成率は75%である。たとえば、研修費用が100万円の場合、75万円が助成される。実質的な負担は25万円となる。
さらに、賃金助成も受けられる。受講者が10名、研修時間が12.5時間の場合、賃金助成は125,000円(10名×12.5時間×1,000円)となる。これにより、企業の実質的な負担はさらに軽減される。
業務効率化の効果
AI研修を受講した従業員は、業務時間の約30〜35%を削減できるというデータがある。情報収集、資料作成、メール対応などの業務が効率化されるためである。1人あたり年間52.8万円の効率化効果が試算されている。
また、受講者の71%が「業務の質が向上した」と回答している。これは、AIを活用することで、より高度な業務に時間を割けるようになったことを示している。単なる時間削減だけでなく、業務の質的向上も期待できる。
組織全体への波及効果
AI研修を受講した従業員が、社内で知識を共有することで、組織全体のAIリテラシーが向上する。これにより、AIを活用した業務改革が、より広範囲に展開される。
また、AI研修を通じて、従業員の学習意欲が高まる。新しい技術を習得することで、自己成長を実感できるためである。これは、従業員のモチベーション向上にもつながる。
グレイトフルエージェントの生成AI研修サービス
株式会社グレイトフルエージェントが提供する生成AI研修サービスは、人材開発支援助成金の対象経費として計上可能である。実際に、2024年以降、多くの企業が助成金を活用して、この研修を導入している。
研修は、ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Geminiの3つの生成AIツールに対応している。全5回構成(各2.5時間、合計12.5時間)のオンライン研修で、週1回×5週間のペースで実施される。対象者は、生成AI未経験者や基礎から学びたい法人担当者である。
カリキュラムは、基礎としてプロンプト設計とAIの基本理解から始まり、応用として自社業務への活用領域の発見、共通業務効率化として文書作成・報告書・議事録・メール対応、専門業務効率化①として営業・人事・総務など職種別活用、専門業務効率化②として現場課題をテーマにした実践ワークで構成されている。
この研修の特徴は、業務に寄り添う構成である。実際の職種・部署単位で事例を選択可能であり、受講中に自社業務を題材にアウトプットを行う設計となっている。また、eラーニングではなく、講師が直接指導するリアルタイム研修である。
導入効果については、業務時間の約30〜35%削減(情報収集・資料作成・メール対応)、受講者の71%が「業務の質が向上した」と回答、1人あたり年間52.8万円の効率化効果を試算という実績が示されている。
この研修は、単なるAI操作講座ではなく、「業務の再設計を促すAI研修」として位置づけられている。企業がAIを”実務で使いこなす”状態をゴールとする法人教育型商材である。
助成金を活用することで、研修費用の75%が還元される。これにより、企業は実質的な負担を大幅に抑えながら、社員のAIスキルを向上させることができる。また、オンライン研修提供と助成金申請サポートをセットで提供しているため、申請手続きの負担も軽減される。
まとめ
AI活用で助成金を受ける方法は、明確である。人材開発支援助成金を活用することで、研修費用の最大75%が助成される。申請から受給までの流れは、制度選定、計画届の提出、研修の実施、支給申請という段階を経る。
申請を成功させるためには、いくつかのコツがある。生成AIを高度デジタル分野として明記すること、オンラインと実務演習のハイブリッド構成を採用すること、賃金台帳に研修時給を明記することである。
助成金を活用することで、企業はコスト削減だけでなく、業務効率化や組織全体への波及効果を得られる。AI研修は、単なる技術習得ではなく、業務の再設計を促す機会である。この機会を活用することで、企業の競争力を高めることができる。
生成AIの導入は、もはや選択肢ではなく、必然である。助成金という仕組みを活用し、社員の能力開発を進めることが、企業の持続的な成長につながる。
実務で使える生成AIスキルを身につけるなら、今がチャンス!




















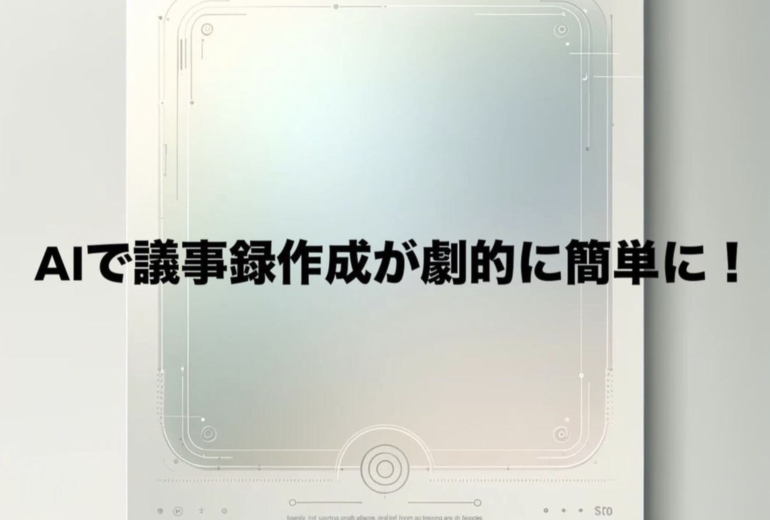
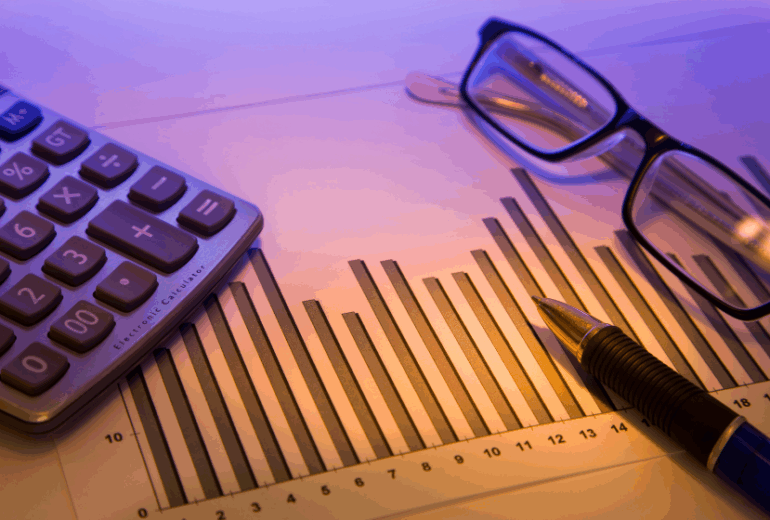





コメント