生成AI研修の決定版。ChatGPT・Microsoft Copilot・Google Geminiを体系的に学び、30日で業務フローを効率化する5ステップを提供します。
日々の業務量が増え続けるなか、生成AIを使いこなせるかどうかが生産性を左右する時代になりました。しかし「何から手を付ければよいか分からない」「時間を捻出できない」と悩むビジネスパーソンは少なくありません。本講座では、対話型の自社研修メソッドを通じて、初学者でも無理なくAI活用スキルを習得できる学習ロードマップを提示します。さらに、人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)の活用方法も解説し、受講費用を抑えながらリスキリングを加速させる仕組みをご案内します。
30日後には、企画書作成やデータ分析など幅広い業務で生成AIを適切に組み込める状態を目指します。まずは本記事で講座の全体像をご確認ください。
目次
5ステップで「学ぶ→使う→成果を出す」学習フロー
Step 1|AIの基礎理解
いきなりツールを操作する前に、AIがどのように動くのかを理解することが、後の応用力を大きく左右します。AIとは何か、生成AIはどのように学習してアウトプットを生み出しているのかといった基本構造を理解することで、「なぜこの出力になるのか」「どう質問すれば精度が上がるのか」が見えてきます。
本講座では、専門用語を極力排除し、図解やたとえ話を使って直感的に理解できるよう設計された導入レクチャーを採用。技術的な背景を知ることで、ツールを単なる便利アイテムとして使うのではなく、戦略的に活用する力が養われます。
Step 2|主要ツールの体験
理解の次は「体験」です。ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Geminiといった代表的な生成AIツールを実際に操作してみることで、それぞれの特徴や得意な分野を感覚的に掴んでいきます。「どうやって質問を投げるか」「どこまで自動化できるか」を自らの手で試すことで、学習のハードルが下がり、モチベーションも高まります。
この段階では失敗や違和感も大切な学びです。本講座では、操作マニュアルだけでなく、よくある失敗例や改善アドバイスも紹介し、初心者でもつまずきにくい導線を整えています。
Step 3|業務への応用
実際の業務に生成AIをどう活かせるかを探るステップです。議事録の要約、提案資料の草案づくり、日報の自動生成など、日々の仕事の中で「手間」と感じていた作業にAIを当てはめてみます。
本講座では、各業務のシナリオに合わせてプロンプト例を提示し、参加者自身が自分の仕事に落とし込める演習を行います。すぐに使えるテンプレートと実例により、「明日から業務で使える」実感を伴ったスキルへと進化していきます。
Step 4|ミニプロジェクト実践
習得した知識を統合し、実務に近いテーマで成果物を作る段階です。個人またはチームで課題を設定し、ChatGPTのAdvanced Data Analysis機能を使ってレポートを作成したり、Copilotでスプレッドシート業務を自動化したりと、実案件に近いワークに取り組みます。
実践フェーズでは、学習の「つもり」から「できる」への転換が起こります。ミニプロジェクトでつまずいた部分こそが、自身の課題を明確にしてくれる貴重なポイント。本講座では講師が個別にフィードバックを行い、スキルの伸びしろを引き出します。
Step 5|情報発信とフィードバック
最後は「インプット」から「アウトプット」へ。学習で得た成果を、社内のプレゼンや社外のポートフォリオとしてまとめ、他者からのフィードバックを受けることで実力をブラッシュアップします。
社内報告、チーム内共有、社外ブログ、ビジネスSNS投稿など、発信方法は自由。講座では「どう見せるか」までサポートし、見栄えのよいスライド作成や文面添削も行います。発信力と振り返りを通じて、自身のAI活用力を客観視し、今後のキャリア形成にも役立てることができます。

30日で完走する学習計画と時間管理術
10日×3フェーズの学習サイクル
本講座では、30日間を「インプット期」「応用期」「定着期」の3フェーズに分け、ステップごとに習得すべき内容とゴールを明確に設定しています。最初の10日間で生成AIの基本原理と主要機能を理解し、中盤の10日間では実際の業務タスクへの応用を体験、そして最後の10日間でミニプロジェクトを通じて実践力を磨いていきます。
各フェーズでは、進捗状況を確認するチェックポイントや、理解度を測るミニテストも組み込まれており、学びを「やりっぱなし」にせず、着実に自分のスキルへと定着させる設計です。フェーズが進むごとに自信が育ち、最終的には「自分で使いこなせる」状態を実感できるようになります。
平日30分・週末60分のリズム
忙しいビジネスパーソンでも続けられるよう、講座では「平日は30分、週末は60分」という現実的な学習時間配分を推奨しています。たとえば、出勤前や就寝前の時間をうまく活用し、短時間でも毎日AIに触れることで、自然とプロンプト設計やツールの使い方が身についていきます。
継続こそが最大の成果を生み出す鍵です。「毎日やる」ことに価値があるとわかれば、少しのスキマ時間も有効活用したくなるでしょう。本講座では、実際のタイムテーブル例や学習のルーティン化を促す仕組みも紹介し、習慣化を後押しします。
時間を生み出す“タスク分解”メソッド
「学びたいけど、時間がない…」という方のために、本講座ではタスク管理の基本から見直す“タスク分解”メソッドを導入しています。メール返信やミーティング準備といった日々のルーチン業務を細かく棚卸しし、重要度・緊急度で仕分けることで、効率的に「学習に使える時間」を生み出します。
講座で提供する「タスク分解シート」では、自分の1日の中に隠れている“学習ゴールデンタイム”を可視化。これにより、仕事と学習がぶつからず、むしろ互いに高め合うライフサイクルを構築できます。
カレンダー連動で可視化する進捗管理
学習の進捗を曖昧な感覚で終わらせないために、講座ではGoogleカレンダーやOutlookなどと連携した「ブロック型スケジューリング」を導入しています。予定を時間帯ごとにあらかじめ登録し、学習が終わったら実績時間も記録することで、達成感とともに改善点も把握できます。
また、講座専用の学習ダッシュボードはカレンダーと自動同期され、週単位・月単位での進捗をグラフで表示。何が計画通りで、何が滞っているかが一目でわかり、自然と自己マネジメント能力も養われていきます。
対話型学習で挫折を防ぐ仕組み
一方通行の動画学習だけでは、疑問点が解決できず挫折してしまうリスクがあります。そこで本講座では、リアルタイムで質問できるQ&Aタイムや、講師・他の受講者とのペアレビューなど、双方向の学びを重視しています。対話型のやりとりを通じて、学びが「実感」として蓄積され、モチベーションも自然と維持されやすくなります。
さらに、人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)の申請や活用も、専任アドバイザーがサポート。「学びたいけど、制度や手続きが不安」という方でも、安心して受講に集中できる体制が整っています。コストを抑えつつ、確実にスキルを身につけたい方にとって最適な環境です。

実務で成果を出す生成AIツール活用術
文章作成──ChatGPTで提案力と速度を両立
日報や企画書、報告書などのテキスト業務は、ChatGPTを「共同編集者」として活用することで、効率と品質を両立できます。ゼロから書く手間を省きつつ、言い回しや構成の工夫を提案してくれるため、時短とクオリティの両面で効果的です。
本講座では、業務別に活用できるプロンプト・ライブラリを提供し、トーンの調整、表現のバリエーション、適切な構成づくりの方法を解説。さらに、生成された文章をどうチェックすべきか、一次情報とAI生成情報の区別の仕方、情報の信頼性をどう担保するかといった「リテラシー面」まで丁寧に指導します。
画像・動画制作──Midjourney・Runwayのクリエイティブ活用
視覚的な訴求力が求められる広告やプレゼン資料では、Midjourneyによるイメージ生成や、Runwayによる動画編集機能が大きな力になります。たとえば、アイデア出し段階でのラフ素材生成や、商品コンセプトのビジュアル化など、従来は外注していた作業を内製化できます。
本講座では、商用利用の際に気をつけるべき著作権や二次利用の注意点、利用ガイドラインの読み解き方までサポート。生成AIが生み出す成果物を「安心して使える」状態に整えるフローも実践を通じて習得します。ポートフォリオ作成にも活用できるスキルです。
データ分析──Microsoft CopilotとChatGPT Advanced Data Analysis
Excelやスプレッドシートを使ったデータ分析業務では、Microsoft Copilotが真価を発揮します。自然言語で「この数値の傾向をグラフで見せて」などと指示するだけで、必要なチャートや要約を即座に提示してくれるため、分析作業のスピードが格段に向上します。
さらに、ChatGPTのAdvanced Data Analysis(旧Code Interpreter)機能を使えば、大容量のCSVデータを読み込み、可視化やトレンド抽出まで対話的に実行可能。SQLやPythonに不慣れな方でも、直感的な操作で「分析できる自分」を実感できます。ノーコード志向の現場にも適したアプローチです。
業務自動化──Zapier連携でルーチンワークを削減
問い合わせ対応、定型レポートの送信、日次集計など、繰り返し作業の自動化にはZapierが有効です。ChatGPTとZapierを連携することで、たとえば「お問い合わせ内容を自動で要約し、Slackに送る」といったワークフローをノーコードで実装できます。
本講座では、Zapierの基本設定からChatGPTとの連携方法まで、ハンズオン形式で丁寧に解説。自社の業務フローにあわせてテンプレートをカスタマイズする実践演習を通じて、「自分で自動化できる力」を育てます。技術者に頼らず現場主導で業務改革を進めたい方に特におすすめの内容です。
成功事例──社内プロセスを変革したケーススタディ
たとえば製造業のB社では、見積もり仕様書の要点をChatGPTで自動抽出し、毎月の作業時間を20時間削減。営業提案の準備時間が短縮され、提案件数も向上しました。また、マーケティング企業のC社では、Midjourneyを活用して広告ビジュアルの初稿を社内で
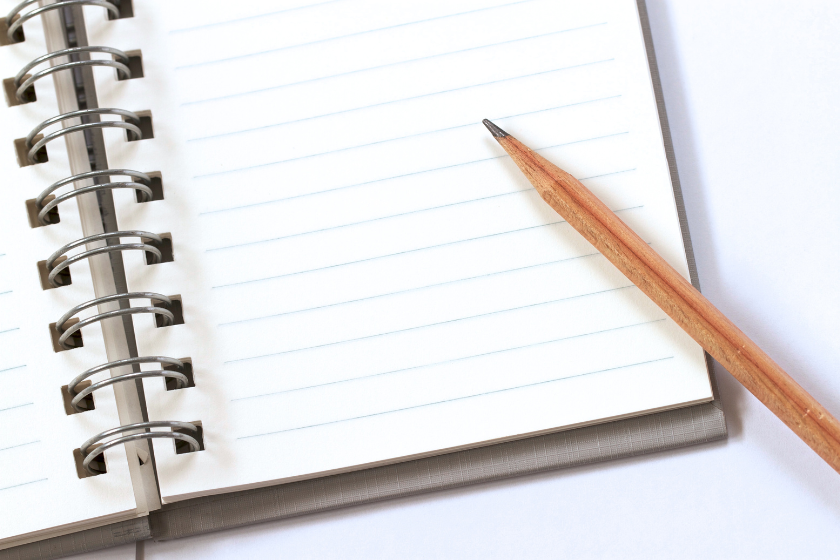
実務で成果を出す生成AIツール活用術
文章作成──ChatGPTで提案力と速度を両立
日報や企画書のファーストドラフトは、ChatGPTを「共同編集者」として活用することで短時間で高品質に仕上がります。本講座ではプロンプト・ライブラリを共有し、トーン調整や事例挿入など実務に即したテンプレートを提供。生成結果は必ずファクトチェックを行い、一次情報の引用可否を確認する習慣を身につけます。
画像・動画制作──Midjourney・Runwayのクリエイティブ活用
広告バナーやプレゼン資料のビジュアル制作では、Midjourneyがアイデア出しとラフ素材生成に役立ちます。さらに、Runwayの動画編集機能を活用することでモック動画を短時間で作成可能です。著作権リスクを避けるため、生成物の商用利用範囲や二次創作制限を確認し、必要に応じてライセンス表記を添えるフローを指導します。
データ分析──Microsoft CopilotとChatGPT Advanced Data Analysis
Excelデータのトレンド把握や異常値検出には、Microsoft Copilotが自然言語操作とグラフ生成を一体化し、レポート作成を効率化します。また、ChatGPTのAdvanced Data Analysis機能では、大容量CSVの読み込みから可視化まで対話的に実行できるため、分析プロセスをノーコード化できます。
業務自動化──Zapier連携でルーチンワークを削減
問い合わせフォームの内容を自動で要約し、社内チャットに送信するワークフローなど、ZapierとChatGPTを組み合わせれば、非エンジニアでも業務効率化の自動化を実装可能です。本講座のハンズオンでは、テンプレートをベースに自社環境へ導入する実践演習を行います。
成功事例──社内プロセスを変革したケーススタディ
たとえば製造業B社では、見積仕様書の要点抽出をChatGPTで自動化し、作業時間を月間20時間短縮。また、マーケティング企業C社ではMidjourneyで広告ビジュアル案を内製化し、外注コストを30%削減しました。これらの事例を通じ、生成AIが「コスト削減」と「提案スピード向上」を同時に実現することを示します。

生成AI時代をリードする第一歩を踏み出しましょう
かつては専門家だけが使いこなすものだった生成AIも、今ではあらゆる職種のビジネスパーソンにとって必須のスキルとなりました。アイデア出し、資料作成、分析業務、マーケティング、プレゼン準備まで、あらゆる業務でAIを味方につけられるかどうかが、今後の仕事の成果を大きく左右します。
本講座の5ステップを30日間で完走すれば、ただの知識や操作方法にとどまらず、「実際の業務に活かせる」実践力が身につきます。そしてその力は、業務の時短や効率化にとどまらず、創造性の発揮や新たな価値創出へとつながり、あなた自身の市場価値や評価も高まっていくことでしょう。
生成AIを活用できるかどうかで、今後のキャリアに大きな差が生まれる時代です。「忙しいから」「技術が苦手だから」と後回しにしていては、変化のスピードについていけません。
本講座では、誰でも無理なく始められるロードマップと、挫折を防ぐ対話型サポート体制を整えています。仕事と両立しながら、無理なく学習を進めたいという方にこそ最適な設計です。あなたの「学びたい」という意志さえあれば、私たちが最後まで伴走します。未来の自分を信じて、今ここから、AI活用の第一歩を踏み出しましょう。
実務で使える生成AIスキルを身につけるなら、今がチャンス!




























コメント